 労働者が業務上の傷病や通勤による傷病で療養のため通常の業務に従事できず賃金を得られなかった場合、休業4日目から業務災害の場合は「休業補償給付」を、通勤災害の場合は「休業給付」を受け取ることができます。
このページでは、労災の休業補償はいくらもらえるか、弁護士がわかりやすく解説します。
労働者が業務上の傷病や通勤による傷病で療養のため通常の業務に従事できず賃金を得られなかった場合、休業4日目から業務災害の場合は「休業補償給付」を、通勤災害の場合は「休業給付」を受け取ることができます。
このページでは、労災の休業補償はいくらもらえるか、弁護士がわかりやすく解説します。
休業補償給付の条件
 労災保険から休業補償を受けるには以下の3つの要件を満たす必要があります。
①業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のため、
②労働することができないため、
③賃金をうけていない、
つまり労働災害によって勤務できず、休業している分の賃金を得られなかった場合に、休業補償が支給されます。
労災保険から休業補償を受けるには以下の3つの要件を満たす必要があります。
①業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のため、
②労働することができないため、
③賃金をうけていない、
つまり労働災害によって勤務できず、休業している分の賃金を得られなかった場合に、休業補償が支給されます。
休業補償の額
 労災保険から支給される休業補償の額は、業務災害の場合の「休業補償給付」も、通勤災害の場合の「休業給付」も同じで、給与基礎日額の60%×休業日数となります。
その他に「休業特別支給金」として、給与基礎日額の20%×休業日数が支給されます。
つまり、休業4日目から給与基礎日額の80%が支給されることとなります。
休業補償給与、休業給付=給与基礎日額の60%×休業日数
休業特別支給金=給与基礎日額の20%×休業日数
なお、業務上の傷病である「業務災害」の場合、労働基準法により、休業初日から3日目までの間は、事業主は平均賃金の60%を支給しなければならないことになっています。
一方、通勤による傷病である「通勤災害」の場合は、事業主の補償についての法的な規定はありません。
労災保険から支給される休業補償の額は、業務災害の場合の「休業補償給付」も、通勤災害の場合の「休業給付」も同じで、給与基礎日額の60%×休業日数となります。
その他に「休業特別支給金」として、給与基礎日額の20%×休業日数が支給されます。
つまり、休業4日目から給与基礎日額の80%が支給されることとなります。
休業補償給与、休業給付=給与基礎日額の60%×休業日数
休業特別支給金=給与基礎日額の20%×休業日数
なお、業務上の傷病である「業務災害」の場合、労働基準法により、休業初日から3日目までの間は、事業主は平均賃金の60%を支給しなければならないことになっています。
一方、通勤による傷病である「通勤災害」の場合は、事業主の補償についての法的な規定はありません。
給与基礎日額とは
 「給付基礎日額」は、原則として労働基準法上の平均賃金になります。
平均賃金は、事故前3カ月間に労働者が得た賃金の総額をその期間の暦日数(れきじつすう)で割った平均賃金(日額)になります。
ただし、臨時に支払われる賃金やボーナスは賃金に含まれませんので注意してください。
※暦日数とは、土、日、祭日を含めた暦(こよみ)の日数となります(例、4月は30日、5月は31日)。
「給付基礎日額」は、原則として労働基準法上の平均賃金になります。
平均賃金は、事故前3カ月間に労働者が得た賃金の総額をその期間の暦日数(れきじつすう)で割った平均賃金(日額)になります。
ただし、臨時に支払われる賃金やボーナスは賃金に含まれませんので注意してください。
※暦日数とは、土、日、祭日を含めた暦(こよみ)の日数となります(例、4月は30日、5月は31日)。
その他の補償
 休業補償のほかにも労災保険では「療養(補償)等給付」「障害(補償)等給付」「遺族(補償)等給付」「傷病(補償)等年金」「介護(補償)等給付」などがあります。
また、労災保険だけではカバーできない不足分を、会社に対し損害賠償を請求することもできるかもしれません。
労働災害(労災)に関するご相談は、初回30分まで無料です。
また、初回のみ10分程度の電話無料相談も行っております。
お気軽にお問い合わせください。
※当事務所では、事故による労働災害のみご相談・受任を承っております。
休業補償のほかにも労災保険では「療養(補償)等給付」「障害(補償)等給付」「遺族(補償)等給付」「傷病(補償)等年金」「介護(補償)等給付」などがあります。
また、労災保険だけではカバーできない不足分を、会社に対し損害賠償を請求することもできるかもしれません。
労働災害(労災)に関するご相談は、初回30分まで無料です。
また、初回のみ10分程度の電話無料相談も行っております。
お気軽にお問い合わせください。
※当事務所では、事故による労働災害のみご相談・受任を承っております。
ご相談 ご質問
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。






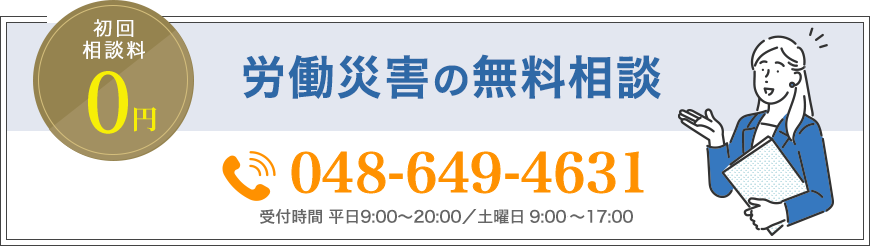
92 レビュー