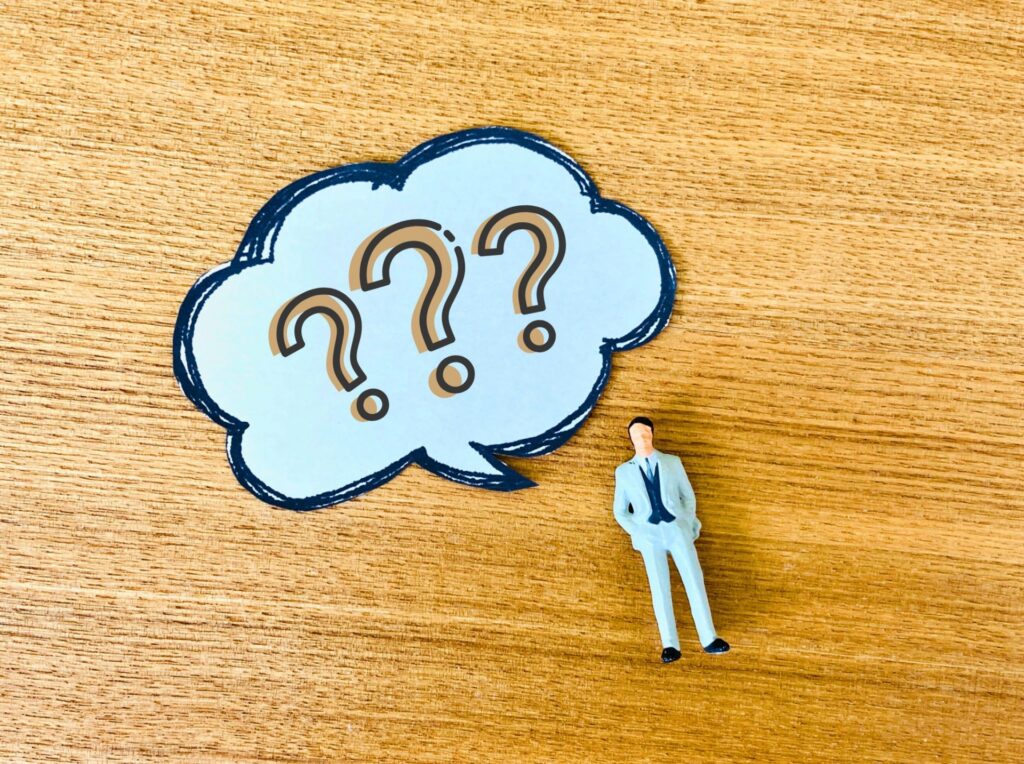 障害等級1級から7級に該当する場合、ご存命である限り、後遺障害が治るするまでは、障害補償年金が支給されます。
支給額は、給付基礎日額(おおまかにいうと、事故前の3ヶ月の給料÷暦日数です) × 313日分(1級)~131日分(7級)です。
では、会社と示談して会社から損害賠償を受けると、将来の障害補償年金の受給がなくなってしまうのでしょうか。
結論からいいますと、「労働基準法77条に定める災害補償である」旨を記載しなければ、支給が停止されることはないそうです(さいたま労働基準監督署見解)。
一方で、第三者行為災害(Eg通勤途中の交通事故)の場合には、災害発生後7年以内に支払うべき部分は受給ができなくなりますが、その後は、再び支給を受けられることになります。
実は、請求できる損害賠償額のうち、障害補償年金の給付として”既になされている金額”(但し、特別支給金を除きます。)については、逸失利益(将来にわたって労働能力を喪失したため得られなくなってしまった利益)という損害費目から控除して請求することになります(労働基準法84条2項参照)。
一方で、障害補償年金の給付として”将来支給が予定されている金額”については、損害賠償請求額から控除する必要はない、と考えられております(最判昭和52年10月25日、最判平成5年3月24日判決)。従って、将来の受給の有無にかかわらず、会社には、逸失利益の全額を請求することが可能です。
しかし、そうすると、実際に損害賠償の支払いがなされた場合、二重に補償されることになってしまいますね。
政府は、そのことを避けるため、保険給付をしないことができ(労災保険法14条2の第2項)、これを「控除」といいます。
では、保険給付がいつまで控除されるのかといいますと、行政通達によれば、「災害発生後7年以内に支給事由の生じた労災保険給付であって、災害発生後7年以内に支払うべき労災保険給付を限度として行う」とされております(平成25年3月29日「第三者行為災害における控除期間の見直しについて」)。
つまり、損害賠償の支払がなされたとしても、7年を経過した後において後遺障害の程度に変更がなければ、給付が再開されることになります。
障害等級1級から7級に該当する場合、ご存命である限り、後遺障害が治るするまでは、障害補償年金が支給されます。
支給額は、給付基礎日額(おおまかにいうと、事故前の3ヶ月の給料÷暦日数です) × 313日分(1級)~131日分(7級)です。
では、会社と示談して会社から損害賠償を受けると、将来の障害補償年金の受給がなくなってしまうのでしょうか。
結論からいいますと、「労働基準法77条に定める災害補償である」旨を記載しなければ、支給が停止されることはないそうです(さいたま労働基準監督署見解)。
一方で、第三者行為災害(Eg通勤途中の交通事故)の場合には、災害発生後7年以内に支払うべき部分は受給ができなくなりますが、その後は、再び支給を受けられることになります。
実は、請求できる損害賠償額のうち、障害補償年金の給付として”既になされている金額”(但し、特別支給金を除きます。)については、逸失利益(将来にわたって労働能力を喪失したため得られなくなってしまった利益)という損害費目から控除して請求することになります(労働基準法84条2項参照)。
一方で、障害補償年金の給付として”将来支給が予定されている金額”については、損害賠償請求額から控除する必要はない、と考えられております(最判昭和52年10月25日、最判平成5年3月24日判決)。従って、将来の受給の有無にかかわらず、会社には、逸失利益の全額を請求することが可能です。
しかし、そうすると、実際に損害賠償の支払いがなされた場合、二重に補償されることになってしまいますね。
政府は、そのことを避けるため、保険給付をしないことができ(労災保険法14条2の第2項)、これを「控除」といいます。
では、保険給付がいつまで控除されるのかといいますと、行政通達によれば、「災害発生後7年以内に支給事由の生じた労災保険給付であって、災害発生後7年以内に支払うべき労災保険給付を限度として行う」とされております(平成25年3月29日「第三者行為災害における控除期間の見直しについて」)。
つまり、損害賠償の支払がなされたとしても、7年を経過した後において後遺障害の程度に変更がなければ、給付が再開されることになります。
ご相談 ご質問
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。






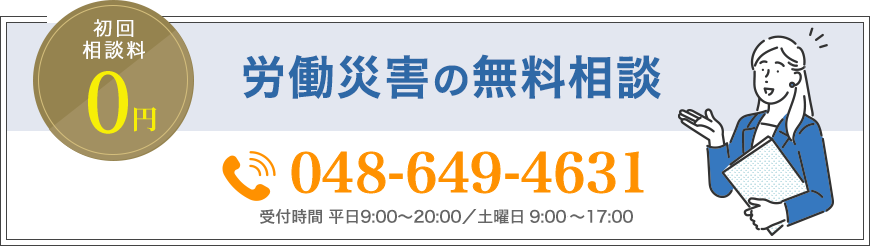
92 レビュー