「もしかしたら、このつらい気持ちや鬱病と診断されたのは職場のせいかもしれない…」
「鬱病や自律神経失調症で後遺障害を認めて欲しい」
そう感じ、労災申請や後遺障害の申請を検討されている方もいらっしゃるかもしれません。
近年、仕事による強いストレスやハラスメントなどが原因で、精神疾患を発症し、労災申請をする方が増えています。
当事務所に実際に相談に来られる方の中には、まだ治療を始めたばかりで、病名も曖昧で、今後の治療の見通しが立っていない方もいらっしゃいます。そうしたケースでは、まだ弁護士の介入が難しく、相談をお断りするケースもあります。
そこで、この記事では、労災による精神疾患で弁護士への相談を考えている方に、まず知っておいてほしいことを説明します。
まずは治療に専念することが重要な理由
「すぐに弁護士に相談して、会社に慰謝料を請求したい」そう考える気持ちも当然かもしれません。
しかし、精神疾患は、他の病気や怪我と異なり、症状が安定するまでに時間がかかることが多いのが特徴です。
焦って法的対応を進めるよりも、まずはご自身の心と体の回復を最優先に考え、治療に専念することが、最終的に最善の結果につながる可能性が高いと考えます。
治療に集中することで、症状の改善が見込めます。また、医師による適切な診断と治療を受けることで、今後の法的手続きに必要な情報も整理されていきます。
知っておきたい「症状固定」という考え方
労災保険には「症状固定」という重要な考え方があります。
■症状固定とは何か?
症状固定とは、一般的に「傷病が治癒せず、症状が安定し、これ以上医療を受けてもその改善が期待できない状態」とされています。
これは、骨折や火傷といった肉体的な傷病だけでなく、精神疾患にも当てはまる概念です。
「労災保険における傷病が「治ったとき」とは、身体の諸器官・組織が健康時の状態に完全に回復した状態のみをいうものではなく、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療(注1)を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態(注2)をいい、この状態を労災保険では「治ゆ」(症状固定)といいます。
したがって、「傷病の症状が、投薬・理学療法等の治療により一時的な回復がみられるにすぎない場合」など症状が残存している場合であっても、医療効果が期待できないと判断される場合には、労災保険では「治ゆ」(症状固定)として、療養(補償)等給付を支給しないこととなっています。」(労働局のパンフレットより)
■症状固定の重要性
症状固定は、労災保険における後遺障害申請の条件になります。
また治療中という場合は、そもそも申請ができません。
つまり、後遺障害とは、治療を続けても残ってしまった障害のことで、その程度に応じて等級が認定されることになります。
そして、後遺障害が認定されて初めて、会社に対して後遺障害に関する損害賠償請求を行うことができるようになるのです。
精神疾患における「症状固定」の特徴
精神疾患における症状固定の判断は、肉体的な傷病に比べて難しい場合があります。
なぜなら、客観的な検査結果が出にくい場合があるからです。
医師は、患者さんの症状の経過、治療の効果、日常生活への影響などを総合的に判断し、症状固定の時期を見極めます。
また、精神疾患は治療期間が長期化する傾向があり、症状が一度改善しても再発するリスクがあることも考慮する必要があります。
どのような治療が行われるのか?
精神疾患の場合、主に精神科や心療内科での治療が中心となります。
具体的な治療法は、患者さんの症状や状態によって異なりますが、一般的には以下のような治療が行われます。
- 薬物療法: 抗うつ薬、抗不安薬、睡眠薬などを用いて、症状を緩和します。
- カウンセリング・精神療法: 専門家との対話を通じて、ストレスの原因や感情の整理、 coping (対処)方法などを学びます。
- 認知行動療法などの専門的な治療: 思考や行動のパターンを見直し、より適応的なものに変えていくための治療法です。
- 休職・復職支援: 必要に応じて休職し、回復状況に合わせて職場復帰を支援するプログラムが行われることもあります。
治療は、急性期の症状を落ち着かせる段階から始まり、徐々に症状を安定させるための維持療法、そして社会復帰に向けたリハビリテーションへと段階的に進められます。
なぜ精神疾患の治療は長引く傾向にあるのか?
精神疾患の治療は、長引くと言われています。長引くのには、いくつかの理由が考えられます。
- 原因の複雑性: 精神疾患は、個人の性格や過去の経験、職場の環境、人間関係など、様々な要因が複雑に絡み合って発症することが多いため、根本的な原因を特定し、解決に導くまでに時間がかかることがあります。
- 回復の個人差: 症状や回復のスピードは人それぞれ大きく異なります。焦らず、ご自身のペースで治療を進めることが大切です。
- 十分な休養の必要性: 心身のエネルギーを回復させるためには、十分な休養が不可欠です。無理に働き続けたり、焦って社会復帰を目指したりすると、症状が悪化する可能性があります。
- 多様な症状と回復への長期的な視点: 精神疾患は、その種類や症状が多岐にわたるため、画一的な治療法や期間が存在するわけではありません。
厚生労働省の示す「精神保健医療福祉の現状について」(https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001374464.pdf)
においても、地域における多様な支援体制の構築や、患者さんの社会参加に向けた継続的な取り組みの重要性が強調されています。
これは、精神疾患からの回復には、個々の状態に合わせた丁寧な治療と、長期にわたるサポートが必要であることを示唆しており、治療が長引く傾向にある理由の一つと考えられます。
後遺障害が残ると会社への請求額が増える可能性
症状固定と診断され、その後、労災保険によって後遺障害が認定された場合、その障害の程度に応じて後遺障害給付が支給されます。
また、会社に対して損害賠償請求を行う際にも、後遺障害の程度は請求額を算定する上で重要な要素となります。
つまり、後遺障害が重いほど、会社への請求額が増える可能性があるということです。
しかし、適切な後遺障害等級認定を受けるためには、症状固定時の状態が非常に重要になります。
しっかりと治療に取り組み、症状が安定した状態で症状固定を迎えることが、適切な後遺障害等級認定につながると考えます
精神障害の労災認定要件
そもそも、精神疾患で労災申請が認められるかにおいては、以下の要件が定められています。
①認定基準の対象となる精神障害を発病していること
②認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か⽉の間に、業務による強い⼼理的負荷が認められること
③業務以外の⼼理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと
※「業務による強い⼼理的負荷が認められる」とは、業務による具体的な出来事があり、その出来事と出来事後の状況が、労働者に強い⼼理的負荷を与えたことをいいます。
⼼理的負荷の強度は、精神障害を発病した労働者が、その出来事と出来事後の状況を主観的にどう受けめたかではなく、同種の労働者が⼀般的にどう受け止めめるかという観点から評価します。
「同種の労働者」とは、発病した労働者と職種、職場における立場や職責、年齢、経験などが類似する人をいいます。
精神障害は、外部からのストレス(仕事によるストレスや私⽣活でのストレス)とそのストレスへの個⼈の反応しやすさとの関係で発病に⾄ると考えられています。
精神障害が労災認定されるのは、その発病が仕事による強いストレスによるものと判断できる場合に限ります。
仕事によるストレス(業務による⼼理的負荷)が強かった場合でも、同時に私⽣活でのストレス(業務以外の⼼理的負荷)が強かったり、重度のアルコール依存があるなどストレスに対する反応しやすさ(個体側要因)に顕著なものがある場合には、どれが発病の原因なのかを医学的に慎重に判断します。
弁護士への相談は「症状固定後」がより効果的
もちろん、労災申請の手続きが複雑で不安な場合や、明らかに会社に責任があると考えられるような状況では、早期に弁護士に相談することも有効な選択肢です
しかし、損害賠償請求を見据えた場合、一般的には症状固定後に弁護士に相談する方が、より具体的な見通しを立てやすくなります。
症状固定前に相談しても、後遺障害の有無や程度が不明なため、弁護士も具体的な損害額を算定したり、会社との交渉方針を明確にしたりすることが難しい場合があります。
症状固定後の状態が明確になってから弁護士に相談することで、弁護士は医学的な診断書や後遺障害等級認定の結果などを踏まえ、より的確な法的アドバイスや交渉を行うことができるようになります。
本コラムのまとめ
労災による精神疾患は、長くつらい道のりとなることもあります。
だからこそ、まずは焦らず、ご自身の心と体の回復を最優先に考えてください。
症状固定という考え方を理解し、適切な治療を受けることが、結果的にあなたにとって最善の解決につながる可能性が高いです。
※当事務所では、お問い合わせが多いことから、現状、労災による精神疾患の場合、「後遺障害等級が認定されている方」のみ受け付けております。
治療中の方、後遺障害等級がでていない方については、ご相談を受け付けることができません。
ご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどお願いします。






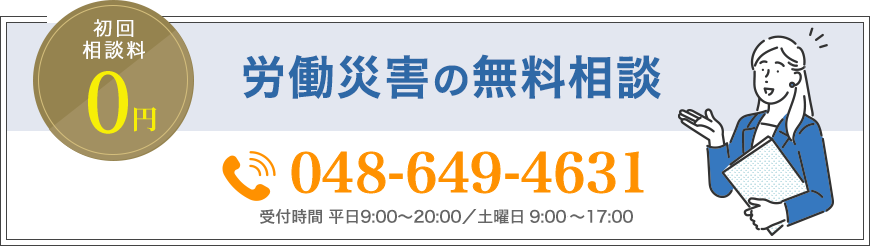
135 レビュー