紛争の内容(ご相談前の状況)
依頼者は、人材派遣会社(派遣元)から食品関係の工場(派遣先)に派遣されていた従業員の方です。
ある日、派遣先の工場内で、正社員(派遣先従業員)の指示を受けて「ホイップ新充填包装機」の作業を行っていたところ、その指示内容が不適切であったことが原因で、稼働中の機械に腕を巻き込まれるという凄惨な事故に遭われました。
この事故により、依頼者様は腕の靱帯や神経を損傷する大怪我を負い、長期間の治療とリハビリを余儀なくされました。また、事故の恐怖から精神的にも深いダメージを受けていました。
今後の生活や補償について大きな不安を抱え、「労災の手続きはどうすればいいのか」「会社に対して責任を問えるのか」と、当事務所にご相談に来られました。
交渉・調停・訴訟等の経過(当事務所の対応)
ご依頼を受けた弁護士は、労災保険の申請段階から全面的にサポートを行いました。
- 障害補償給付の申請サポート(労災認定)
後遺障害の認定において重要なのは、「事故状況の正確な把握」と「医学的な立証」です。
弁護士はプロの視点から事故の詳細な状況を確認し、医師と連携して障害の状態を正確に反映した書類を取り纏めました。
その結果、靱帯や神経の損傷による機能障害等が認められ、「障害等級12級6号」に認定。労災保険から約130万円以上の給付金が支払われました。 - 企業への損害賠償請求(責任の追及)
労災保険からの給付だけでは、被害者が受けた精神的苦痛(慰謝料)や将来の逸失利益を補うには不十分でした。そこで弁護士は、会社側への損害賠償請求に着手しました。
まず、派遣元と派遣先の双方に通知を送付。派遣元を通じて両社の法律関係や契約内容を徹底的に調査しました。
その結果、本件事故は派遣先の従業員による不適切な指示や、機械の安全管理体制の不備が直接的な原因であるとして、「派遣先企業に明確な安全配慮義務違反(法的落ち度)がある」ことを特定しました。 - 派遣先企業との交渉
責任の所在を派遣先に絞り込み、弁護士は損害賠償請求の交渉を開始しました。
具体的には、通院交通費、主婦休業損害、後遺症逸失利益、後遺症慰謝料、通院慰謝料といった各損害項目を詳細に計算し、これらを積み上げた正当な賠償額を請求しました。
派遣先企業は当初、責任の範囲について争う姿勢を見せましたが、弁護士が調査に基づいた法的根拠を突きつけ、強気で交渉を進めました。
交渉は、派遣先の顧問弁護士との間で、面会して現状を細やかに伝えるなどし、理解を得る事にも努めました。
本事例の結末(結果)
弁護士による粘り強い交渉の結果、派遣先企業は自社の安全配慮義務違反を認めました。
最終的に、労災保険からの給付(約130万円以上)とは別に、派遣先企業から依頼者様へ「解決金として500万円」を支払わせる内容で合意に至りました。
この500万円には、弁護士が主張した通院交通費、主婦休業損害、後遺症逸失利益、後遺症慰謝料、通院慰謝料の各損害が十分に反映されています。
労災給付と合わせると十分な補償額となり、依頼者様は経済的な不安を解消し、治療と生活再建に専念できる環境を勝ち取ることができました。
本事例に学ぶこと(弁護士からのアドバイス)
- 派遣社員の事故は「派遣先」にも責任がある
派遣社員の方が事故に遭った場合、「雇い主である派遣元」だけでなく、「実際に指揮命令をして働かせている派遣先」にも安全配慮義務違反(損害賠償責任)を問えるケースが多くあります。 - 「主婦休業損害」など、見落としがちな損害も請求可能
本件のように、兼業主婦(主夫)の方の場合、お仕事の休業補償だけでなく、家事に支障が出たことに対する「主婦休業損害」も請求可能な場合があります。
会社側が自発的にこれを認めることは稀ですが、弁護士が介入することで、交通費や慰謝料、逸失利益と合わせて正当に請求することが重要です。
会社(特に派遣先)相手の交渉は、個人では非常に困難です。労災事故に遭われた際は、申請段階から専門家である弁護士にご相談ください。
弁護士 時田 剛志






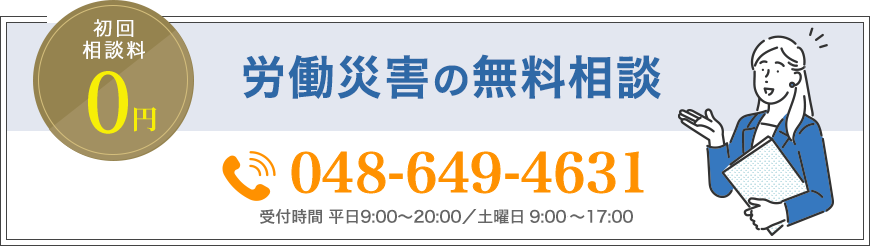
140 レビュー